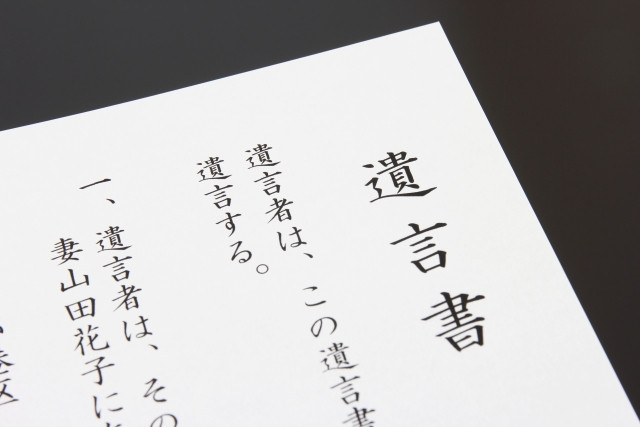‐自筆証書遺言書の取り消し(撤回)の方法と注意点とは!?‐
遺言書を作成したものの、財産の総額や内容が変化するなどにより遺言書を取り消ししたい、変更したい、ということもあるかと思います。
遺言書の取り消しは「撤回」呼ばれ、いつでも可能ですが、いくつかの注意点があります。
今回は、自筆証書遺言の撤回方法をご紹介します。
遺言書はいつでも撤回できる
民法1022条では、作成した遺言の撤回が認められています。
遺言書は遺言者が亡くなったあとの意思を実現することを目的としているため、遺言者はいつでも自由に内容の変更や取り消しが可能です。
ここで言う「撤回」とは、まだ効力が生じていない意思表示に対してのものです。
遺言書は遺言者が亡くなるまでは効力が発生しません。
つまり、遺言者が存命の間であればいつでも撤回ができます。
自筆証書遺言の撤回方法
遺言書を破棄する
自宅で保管している自筆証書遺言の場合、該当する遺言書を破棄すれば遺言書自体がなくなりますので、取り消しと同じ効果になります。
新たに遺言書を作成する
遺言書が複数存在する場合、新しい日付の遺言が優先されます。
つまり、新しく遺言書を作成すれば、以前の遺言は効力が失われます。
また、撤回の旨を記載すれば全部または一部の撤回が可能です。
遺言の内容を全部撤回したい場合は「令和〇〇年〇〇月〇〇日付の自筆証書遺言を全部撤回する」と新しい遺言書に記載します。
一部撤回したい場合は撤回したい部分を具体的に記載し、これを撤回する旨と改める内容を記載します。
ほかの方式の遺言での撤回も可能
遺言書の撤回は遺言の方式に従っていれば良く、自筆証書遺言を撤回するときに必ずしも自筆証書遺言の方式でなければならないという決まりはありません。
遺言書の方式に優劣はありませんので、ほかの方式の遺言でも撤回できます。
財産処分による撤回擬制
遺言により引き継ぐ旨記載していた財産を、その後生前処分した場合、その部分の遺言を撤回したものとみなされます。
これを「財産処分による撤回擬制」と言います。
たとえば、遺言書に自宅の土地と建物を長男に相続する旨を記載したあとに自宅を売却した場合は、この部分の遺言は撤回したものとみなされ、長男は自宅を相続できません。
また、自宅を売却した場合、売却代金が預金口座に入金されているケースが多くありますが、売却代金を相続できるのは預金口座を相続する人であり、長男とは限りません。
長男に自宅の売却代金を相続させたい場合は、入金された預金口座の相続人に長男を指定する必要があります。
遺言書を撤回する際の注意点
「遺言書の撤回」は撤回できない
遺言書を撤回したら、それを撤回してもとに戻すことはできません。
改めて撤回したい場合はあらたに以前と同じ内容の遺言書を作成する必要があります。
撤回した遺言書が無効になる可能性がある
自筆証書遺言で特に注意しておきたいのが、遺言書が形式不備により無効となるケースです。
撤回した遺言書が無効となった場合、以前作成した遺言書が有効になるだけでなく、相続トラブルの原因となります。
できるだけ行政書士などの専門家にサポートしてもらい、不備のない遺言書を作成するようにしましょう。
遺言書の紛失リスクに注意
自筆証書遺言書を自宅で保管している場合、遺言書が紛失してしまったり、遺族に見つけられないままになってしまうリスクがあります。
このようなことを防ぐため、家族に遺言書の存在を知らせておく、法務局の保管サービスを利用する、などの対策をしておくと安心です。
遺言書の撤回は公正証書遺言がおすすめ
遺言書の撤回は、形式不備により無効になると前の遺言の内容で財産の分配を行うことになります。
遺言書の撤回が無効となると、遺言書が存在していないときよりも相続で揉めてしまうケースがあります。
公正証書遺言は公証人が作成するため、不備による無効にならない点が大きなメリットです。
トラブルを防ぐためにも遺言書の撤回は公正証書遺言を作成するのがおすすめです。
遺言書はいつでも撤回可能
遺言書はいつでも撤回が可能ですので、取り消したい内容や変更したい内容がある場合はご紹介した方法を取れば変更が可能です。
ただし、自筆証書遺言の場合は形式不備により無効となってしまうリスクもありますので、行政書士などの専門家のサポートを受けながら作成すると安心です。