遺言書の取り消し方法:相続トラブルを防ぐための正しい手順を紹介
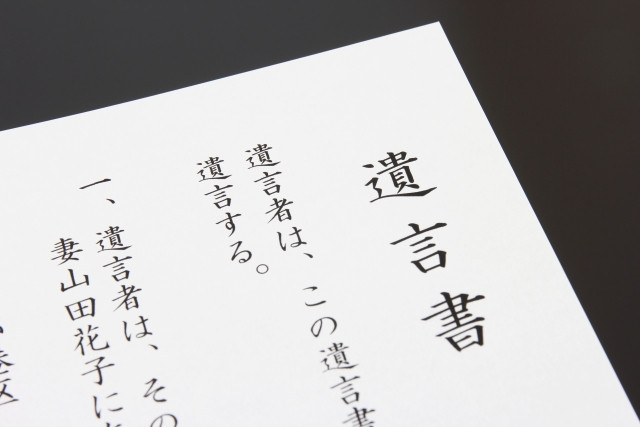
遺産分割の方法などを指定できるのが、遺言書の特徴です。
作成時にルールを守らないと無効になるのと同じで、取り消す時にも正しい方法を使わないとなりません。
取り消しに失敗すると、本人の意思が反映されない結果になるので気を付けましょう。
この記事では、相続トラブルを防ぐために知っておきたい、正しい遺言書の取り消し方法を紹介していきます。
1.遺言の撤回・取り消しの基本知識
遺言書の作成は任意ですから、作った後の撤回・取り消しはいつでも自由です。
特に誰かの許可が必要と言うことはありません。
自筆証書遺言も他の方式も同じで、自由に取り消せます。
ただ、民法などに規定された手続きを踏んで、取り消したことが家族にとって明確になるよう、配慮が必要です。
遺言を取り消すには、主に3つの方法があります。
廃棄と、新しい遺言の作成、そして、既存の遺言書を修正する方法です。
いずれにも一長一短があるので、注意点を確認して下さい。
2.廃棄する時は悪意ある者への対策が重要
廃棄する方法はシンプルで、遺言書を捨ててしまえば手続きは完了です。
自身で保管している遺言書を廃棄すると、最初から何もなかったことになります。
まだ、誰にも遺言書を作ったことを伝えていない時や、作成したのが1通の場合は手軽な方法でしょう。
燃やしたりシュレダーにかけたりして確実に処分すると、中身を復元される危険性がないのでおすすめです。
3. 廃棄による遺言書の取り消しは注意点が多い
ただ、廃棄による方法は弱点があります。
まず、公正証書遺言には使えません。
公正証書遺言は公証役場に保管されており、自身で廃棄できないのです。
手元には原本がないため、公正証書遺言は別の方法を使います。
また、複数枚の遺言書がある時も注意が欠かせません。
廃棄した部分だけ取り消したことになるため、処分し忘れている分があると危険です。
他には、遺言書を作ったことを誰かに伝えた場合も、気を付けましょう。
撤回したことを明らかにするため、廃棄した旨を伝えるようにします。
ただ、遺言書が有効になるのは、作成者が死亡した時ですから、何十年先になるかわかりません。
このため、遺言書があったかなかったかわからなくなり、ひと騒動起こる可能性もあります。
撤回した証拠を残すためには、従前の分を取り消す内容の、新しい遺言書を作成しておくと安心です。
4.別の遺言書を作成して取り消す方法
従前の遺言を取り消す遺言書を作ると撤回した証拠が残るのがメリットと言えます。
自筆証書遺言はもちろん、公正証書遺言などの他の方式の遺言書も、従前の遺言を取り消す旨の遺言書を作成可能です。
同じ方式でなくても構わないため、例えば、公正証書遺言を自筆証書遺言で取り消すこともできます。
新しい遺言書では、従前のものを全部撤回することも、一部の内容だけ取り消すことも自由自在です。
なお、一番後に作った最新の遺言書が有効になるので、複数の遺言書があっても、全て探して処分する手間も必要ありません。
新しい遺言書が古いものの内容に抵触する分だけ、撤回したことになります。
5.遺言書を訂正する方法
軽微な修正なら、作成した遺言書を直接、修正する方法もありますが、これは手続きが厳格なので気を付けて下さい。
書き加えるのも削除するのも、一定の要式が求められており、適当に訂正すると取り消しの効果が発揮されません。
更に、遺言書の原本が手元にない場合、気軽に訂正できないのも注意点です。
役場に行くか、自筆証書遺言などで撤回しましょう。
6.トラブルを未然に防止するには
遺言書は色々な法的制約があります。
このため、作成時はもちろん、修正や撤回を検討する際も専門家に相談するのがおすすめです。
いざと言う時に遺言書の効力が生じなかったり、取り消しができていなかったりすると、思わしくない結果になるでしょう。
加えて、遺留分や、不動産などの資産が多い時は相続税なども問題になります。
生前から相続対策を進めるためにも、専門家に相談するのが安心です。
まとめ
遺言書の取り消しの流れを解説してきました。
廃棄する方法が簡単ですが、取り消した証拠が残らないのが不安材料です。
いずれにせよ、取り消す際には法律知識を求められるので、気を付けて下さい。
相続に関しては遺産分割や相続放棄の可能性など、色々な心配事がありますので、
多彩なケースに対応してきた実績のある事務所に相談するのがおすすめです。
