遺言書の内容変更をしたいときの手続き方法と注意しておきたいこと
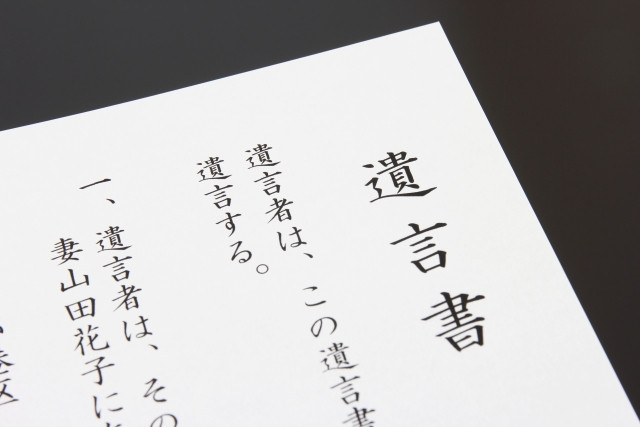
遺言書を書いた後になって考えが変わるということはよくあることです。
遺言書は相続の開始前、つまり、被相続人が亡くなる前であればいつでも内容を変更したり、
撤回することが可能です。
そこで、遺言書の内容変更をする方法や注意しておきたいことを解説します。
遺言書の内容の変更は相続が起こるまでならいつでも可能
「民法1022条(遺言の撤回)」では
「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる」
としています。
つまり、遺言書はご本人が亡くなるまではどのタイミングでも内容を変更したり、撤回することが可能です。
遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言がありますが、全ての遺言書で内容変更が可能です。
また、公正証書遺言から自筆証書遺言等、遺言書の種類を変更もできます。
遺言書の内容変更・撤回の方法
自筆証書遺言の場合、内容の変更・撤回をしたい場合は元の遺言を破棄して新たに遺言を作成すれば済みます。
公正証書遺言の場合は以下のように変更・撤回を行います。
遺言書の内容を変更したいとき
一度作成した公正証書遺言を変更したいときは、新しく遺言書を作成し、
その遺言書の中で先の遺言書の中の変更したい部分を撤回する旨を明記し、新たな遺言内容を記します。
変更する際の文例は以下の通りです。
「遺言者○○は令和○年○月○日作成 令和○年第○号公正証書遺言中、
第○条の「妻●●に相続させる」とする部分を撤回し、
「長男▲▲に相続させる」と改める。
その余の部分はすべて上記公正証書遺言記載の通りとする。」
遺言書の内容を全部撤回したいとき
公正証書遺言を撤回したいときは以下の文言で遺言書を撤回する旨の書面を作成します。
「○○は、令和○年○月○日作成 令和○年第○号公正証書遺を全部撤回する。」
遺言書の内容変更をする際の注意点
遺言書は先に作成されたものより後に作成されたものが有効となります。
内容が矛盾した場合、後に作成したものが有効になる、ということは知っておきましょう。
また、前に書いた遺言書は、相続人が混乱しないように破棄しましょう。
一度撤回した遺言は復活しません。
遺言が撤回された場合はその後に「遺言の撤回をさらに撤回する」
という事が行われたとしても撤回された元の遺言が効力を回復することはありません。
ただし「撤回の撤回」を行った遺言者の意思が、
元の遺言を復活させることを希望するものであることが明らかな場合には
例外的に元の遺言が効力を回復する場合もあります。
遺言書作成を行政書士に依頼するメリット
法律的に有効な遺言書を作成できる
遺言書は自分で作成すれば費用はかかりません。
しかし、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用しない場合、
亡くなった後に裁判所の検認手続きなど遺言の執行までに手間がかかったり、
内容が遺言として有効ではないものの場合、遺言書が無効になる可能性があります。
行政書士に依頼すれば専門家の判断のもと、法律的に有効な遺言書を作成することができます。
作成費用を抑えることができる
行政書士は他の専門家に比べて比較的少ない費用で遺言書作成を行っています。
相続人が大勢おり、財産の分割方法が複雑になる場合は行政書士では扱えない業務がありますが、
それほど相続が複雑でない場合は行政書士に依頼するのがおすすめです。
相続・遺言相談の得意な行政書士に依頼するのがポイント
ここまで行政書士に遺言書作成を依頼するメリットをご説明しましたが、気を付けるべきことがあります。
それは、すべての行政書士が遺言書作成や相続の実務に精通しているとは限らない点です。
遺言書作成を依頼する際には相続・遺言書作成に関する業務の得意な行政書士に依頼するのがポイントです。
遺言書はいつでも内容変更が可能
遺言書を書いた後、遺言書の内容が実現されるまでには10年、20年など相当な期間があることが多く、
その間、家族が増えることも減ることもあり、事情が変わることも当然起こり得ます。
遺言書は何回でも書く事ができ、最新の内容が有効とされますので、
その時の事情に応じて内容を変更する事ができます。
遺言書の作成に関しては行政書士も相談を受け付けていますので、お気軽に問い合わせてみてくださいね。
