ー遺言書は何歳から書ける?作成するときの適切なタイミング解説ー
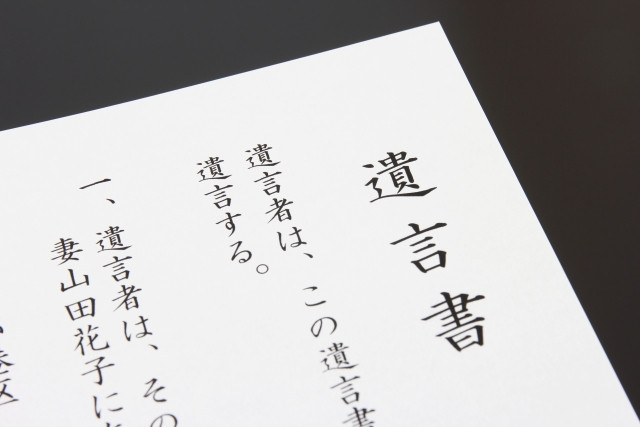
自分の死後の希望や財産分与に関して遺言書を残したい場合、何歳から作成できるのか疑問に思う方もいるのではないでしょうか。
遺言書は、ある程度年を取ってから書くイメージを抱いている方が多いかもしれませんが、15歳から作成できます。
一般的には人生の節目となるタイミングに合わせて書いておくと、相続のトラブル防止につながるでしょう。
本記事では遺言書は何歳から書けるのか、作成のタイミングに関しても詳しく解説します。何歳から書いたらよいのかわからない、または遺言書作成のタイミングを知りたい方は参考にしてください。
遺言書は何歳から書けるのか
遺言書は民法第961条により「十五歳に達した者は、遺言をすることができる。」としています。
意思能力の低い小学生だと遺言能力はありません。また高齢になり、認知症を患うと判断能力を失ってから遺言書を作成しても無効となるでしょう。
自分が書いた内容を理解できる15歳以降なら、何歳からでも遺言を遺せるということです。
また若いうちに書いておくと情報収集ができ、状況変化により手直しもできます。
遺言を書くタイミングは何歳から?
遺言書は15歳以降なら何歳からでも、いつ書いてもよいのではなく適切なタイミングがあります。
人生の節目となる、重要なイベントがあったときに遺言書を作成するのがおすすめです。
結婚や出産
結婚や出産は家族構成、資産状況が変化するタイミングです。配偶者や子どもなど人数が増えると、遺産の分配を考える必要があります。
遺言書を作成しておくと遺産相続に関するトラブルを未然に防止できるでしょう。
家族内で揉めごとが起きないように、将来を守るためにも遺言書は重要です。
住宅の購入
住宅を購入すると資産や負債が増加し、相続の対象となる財産が増えます。遺言書がないと誰に相続するのか、維持管理はどうするのかなどトラブルに発展するおそれがあります。
自分の死後、住宅を譲りたい方がいるなら遺言書に記載しておくことが重要です。
遺言を書くことで、住宅の相続や維持管理に関する問題を未然に防ぐことができます。
住宅を購入したときには、将来の相続に備える必要があります。
定年退職
仕事を定年退職すると、収入や社会的地位が変化します。財産が大きく変わる節目のため、家族に対して遺言を遺しておくと安心です。
遺言書の作成は財産管理や遺産分配を計画的に行うためにも重要です。
また定年退職する頃は判断能力も十分にあるため、元気なうちに遺言書を書くとよいでしょう。
家族構成の変化
結婚や出産のほか、離婚や再婚などにより家族構成が変化すると遺産分配に影響を及ぼします。
たとえば子どもが独立したり、親が高齢化したりすると遺言書の見直しが必要です。相続争いを未然に防ぐためにも適切な遺言書を作成する必要があります。
自分や家族が罹患
何かしらの病気やケガにより、突然の死や意識不明の状態に陥る可能性はゼロではありません。事前に遺言書を作成しておくことで、死後の意思を伝えられます。
遺言書がないと本人の意思がわからず、家族も対応に困るケースがあります。
自分や家族が罹患したときには早めに遺言書を作成しておき、家族の負担を減らすことが大切です。
まとめ
遺言書は何歳からでも書けるわけではなく、15歳になったら作成できると民法で定められています。
若いうちに書いておくと有益な情報を得られるほか、状況に応じて書き直すことも可能です。また高齢になってから書くと意思能力が低下するおそれがあるため、体が元気なうちに取り組むほうがよいでしょう。
ただし、15歳以降は何歳からでも遺言書を作成してよいのではなく、適したタイミングがあります。
結婚や出産などで家族構成が変わったとき、住宅の購入や定年退職で資産が変化したときなどが遺言書を書く節目です。
相続トラブルを防ぐためにも、早いうちから遺言書を書いておきましょう。
